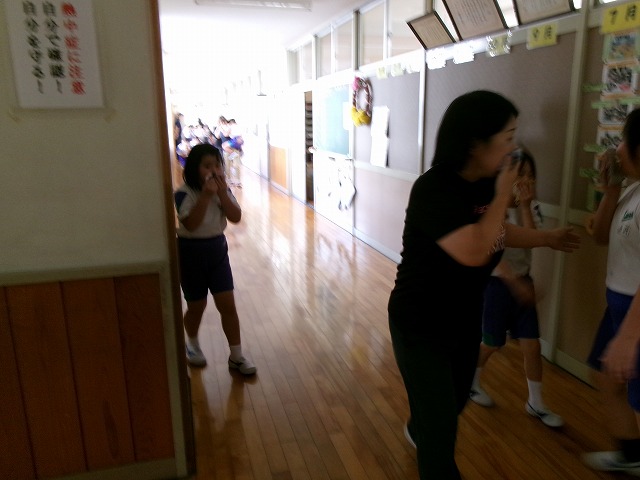消防署の方をお招きして、火災を想定した避難訓練を行いました。
今回は授業中ではなく「ふれあいタイム」の時間という想定です。子ども達には、その時間に避難訓練があることは伝えてありますが、火災発生場所は教職員も含めて知らされていません。さらに、模擬の煙を発生したりするなど、より現実に近い訓練にしました。
今回は、図工室から煙が出ました。子ども達が発見し、教員に伝え、非常ベルが押されました。
今回は、放送設備も使えない想定で、メガホンや声で避難を呼びかけます。

避難完了しました
休み時間の想定ですので、教員が近くに居ない場合も考えられます。本校のように、教員の数が限られている学校では、高学年が低学年をサポートすることが重要になってきます。これまでの「お」さない、「は」しらない、「し」ゃべらない「も」どらない、に加えて、「て」いがくねんゆうせん、の「お・は・し・も・て」を確認しました。

消防署の方からのお話
消化器の使い方も教えていただきました。

代表が「水消火器」で体験しました
今回は、教員側も管理職不在の想定での訓練で、初期消火や通報、児童の誘導などの課題を見つけることができました。また、児童側も日時がわかっている上での訓練でしたので、落ち着いて行動することができましたが、非常時に同じような対応ができるように、今後も想定を現実に近づけながら、訓練を重ねていく予定です。